診療科のご案内
血液内科
当科では,造血器腫瘍をはじめとする血液疾患を主な治療対象として,3人体制で外来・入院診療を行っています。血液内科病床は全44床で,全室個室です。免疫抑制状態にある患者さんが多い中,感染症のリスクがより低い環境で安心して治療を受けて頂いています。さらに,クリーン管理区域内に5床の無菌病床を備えています。



当科入院患者さんの疾患内訳はおおよそ、急性白血病10%、悪性リンパ腫30%、多発性骨髄腫15%、骨髄異形成症候群10%と、造血器腫瘍が約70%を占めています。最近の造血器腫瘍に対する治療の進歩は目覚ましく、化学療法(殺細胞性抗癌剤)、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、自家および同種造血幹細胞移植に加え、免疫細胞療法(CAR-T療法、二重特異性抗体療法)も日常診療として施行できるようになりました。その結果、生存率の向上と副作用の軽減が得られ、以前は緩和的治療しか選択できなかった高齢患者さんや、大変厳しい病状の方にも有効な治療が施行できるようになってきました。当科ではこれらの治療の中から、それぞれの患者さんに最適なものを提案・選択し、治療を施行しています。同種造血幹細胞移植、CAR-T療法が必要な患者さんについては、大学病院と連携しながら治療しています。また、一部の固形腫瘍に対する薬物療法も大学病院との連携のもとで専門的に施行しています。
清田区内には当院以外に血液内科を専門とする病院がありません。地域の患者さんはもちろんのこと、お隣の北広島市、恵庭市、千歳市からも多くの患者さんが来院されています。高齢化社会を背景として血液疾患の治療を必要とする患者さんが年々増加しています。当科で入院加療を行う患者さんもここ数年、増加傾向です。患者さんのQOLを考慮し、良性疾患と悪性疾患(造血器腫瘍)のいずれにおいても、入院加療が必要な患者さんは入院して頂き、外来治療が可能な方は外来でと、病状や希望に合わせて治療を継続しています。

血液内科の対応疾患
- 急性骨髄性白血病
- 急性リンパ性白血病
- 慢性骨髄性白血病
- 慢性リンパ性白血病
- 骨髄異形成症候群
- 真性多血症
- 本態性血小板血症
- 骨髄線維症
- 悪性リンパ腫
- 多発性骨髄腫
- 再生不良性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 溶血性貧血
- 特発性血小板減少性紫斑病 など
-
血液の病気
血液細胞
全身を流れている血液には、白血球、赤血球、血小板という3種類の細胞があります。これらの細胞は、造血幹細胞とよばれる、大もとになる細胞から、骨の中にある骨髄という場所で造られています。白血球は細菌やウイルスといった外敵と闘い、赤血球は全身の細胞に酸素を運搬し、血小板は出血した際に血を固め、出血を止める働きをします。
当科では、これら3種類の血液細胞が異常を来すことによって起こる様々な血液の病気を主に治療しています。- 白血球の病気
白血球は、細菌やウイルスと闘う兵隊さんの働きをしており、これらの感染症では、白血球の増加が多く見られます(一部のウイルス性感染症では、減る場合もあります)。健康診断で白血球増多を指摘されて、受診される患者さんは、頻度的にも、風邪(感染症)などに伴う白血球増多症が多く、再検査した際の採血では、白血球は正常化しており、一過性の白血球増多であったことがわかります。ただし、稀ながら、悪性疾患もあります。悪性疾患には、白血球が「がん化」してどんどん増殖する白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった病気があげられます。これらは、造血器悪性腫瘍と総称され、「血液のがん」といえるものです。また、骨髄異形成症候群という白血病の前段階とされる病気もあり、これらは、当科で扱う中心的な病気です。
白血球には、好中球や、リンパ球などの様々な種類があり、またこれらの白血球は、造血幹細胞からいくつかの段階を経て(分化とよびます)作られますが、上に述べた様々な造血器腫瘍の違いは、どの種類の、どの段階の白血球が腫瘍になったものか、ということで名称が変わります。たとえば、造血幹細胞に近い未熟な白血球のある段階で腫瘍化して、骨髄の中で急速にふえるのが急性白血病(急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病)、リンパ球とよばれる白血球が、全身に分布するリンパ節で増殖するのが悪性リンパ腫、免疫グロブリンという蛋白質を作る形質細胞とよばれる白血球が、骨髄の中で増殖するのが多発性骨髄腫です。慢性骨髄性白血病は、造血幹細胞に近い未熟な白血球が分化能をもちながら腫瘍化した病気です。急性=急激、慢性=緩か、という意味ではありませんが、病態的には、急性は進行が早く、慢性は比較的緩やかに進行します。ただし、慢性白血病も進行すると急性白血病のようになり、急性転化といいます。
これらの病気は命にかかわりますが、幸いなことに、抗がん剤治療(化学療法とも言います)、放射線療法、骨髄移植といった治療を組み合わせることにより、治癒に導くことも可能です。
当科では、こうした造血器腫瘍の治療が診療の中心になります。 - 赤血球の病気
赤血球が減った状態が貧血です。赤血球が減る原因により、「○○貧血」と名のつく様々な病気があります。最も頻度が多い貧血は、急激な成長やなんらかの出血によって鉄分が不足して起こる鉄欠乏性貧血です。
男性では、胃癌、大腸癌などの悪性腫瘍や、胃潰瘍、大腸ポリープからの出血が原因のことが多く、女性では、生理による出血、子宮筋腫で認めます。その他、赤血球の材料であるビタミンB12、葉酸が不足した場合には、赤血球の大きさが大きくなる(大きくなりますが、数は減っています)巨赤芽球性貧血も知られています。造血幹細胞の異常によって、赤血球のみならず白血球や血小板も作られにくくなる再生不良性貧血、きちんと造られたにもかかわらず赤血球がさまざまな原因で壊れてしまう溶血性貧血などがあります。これらは、自覚症状では、だるさ、動悸、立ちくらみなどの、いわゆる貧血症状という共通の状態を引き起こしますが、原因が異なるため、治療の方法も大きく異なります。
赤血球が増えた状態が赤血球増多症です。造血幹細胞の異常で、赤血球が増える病気は、真性赤血球増多症であり、治療としては、体から血を抜く、寫血療法を行います(1回につき、200ml~400ml)。寫血で効果が不十分な場合には、ハイドレアなどの抗がん剤を使用します。
また、タバコ、肥満、ストレスが原因の二次性赤血球増多症という病気もあり、二次性の増多症では、禁煙、ダイエット、ストレス解消が重要です。 - 血小板の病気
様々な原因で血小板の数や機能が低下すると、紫斑(皮下出血)ができやすい、血が止まりにくい、といった易出血状態になります。血小板が減る病気で比較的多いものが、薬剤性血小板減少症で、薬剤による副作用で、血小板が減る病気です。治療は、原因となる薬剤を中止することですので、自分が飲んでいるお薬は、どこの病院で、いつ処方されたのかを把握していることが重要です。お薬の名前は、難しく覚えられない場合が多いですが、薬手帳は準備しておくことが治療の近道になります。
その他、血小板減少で、代表的な病気は、特発性血小板減少性紫斑病です。何らかの免疫異常で、自分の血小板を攻撃する抗体(免疫グロブリン)を自分で作ってしまうことにより起こります。また、比較的頻度は少ないですが、全身に血栓ができることで血小板が減る血栓性血小板減少性紫斑病という病気もあります。発熱、腎機能障害、精神症状、貧血を伴うことがありますが、これらの症状が揃わず、診断が難しいこともあります。
血小板が通常より増える病気の代表的なものは、本態性血小板血症があげられます。
一方、さまざまな原因で血管の中で血が固まってしまう血栓症は、脳梗塞や心筋梗塞、肺塞栓と、重篤な病態の原因になります。このような血栓が血管の中にできるのを防ぎ、心臓や脳などの重篤な障害を防ぐうえでも、当科は重要な役割を果たしています。
- 白血球の病気
- 医師紹介


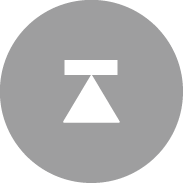 PAGE TOP
PAGE TOP